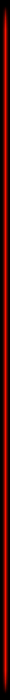OVER THE RAINBOMB
Free Electro
(Distributed by Victor Musical Trading inc.)
Produced by Toshinori Kondo
Contents
- Fire makes darkness 2003 (8'05")
- 大人の戦争わかんない -Kids don't make the war- (6'56")
- Over the rainbomb (7'02")
- Eternal voice (5'34")
- Mixed tears (7'04")
- Beyond the sorrow (7'03")
All songs are composed by Toshinori Kondo
- Sampled materials -- Maleem Mahmoud Ghania and Ensenble (Morrocco) performed at "World Festival of Sacred Music Hiroshima 2001" ...for #1
- Tibetan children's singing in Ladak, Himalaya ...for #3
- Raj-Rang (India) performed at "WFSM Hiroshima 2001" ...for #4

Artists
FREE ELECTRO
- 近藤等則 Toshinori Kondo : El-Trumpet, Voice, Programming
- DJ Sahib : Turntable, Effects
- Eiji : Guitar
- Spirit Jack : MC 909
Recorded and Mixed by Toshinori Kondo at Kondo Sonic Body Lab. Studio (Kawasaki) on March - May 2003
CD Jacket Title Calligraphy : 黒田征太郎 Seitaro Kuroda
Art direction by Kitazawa-office
Designed by Bitamin K & Kitazawa-office
This album is available at "Blow The Earth in Japan" Official Site
『文明は争いを巻き起こすが、文化はMIXしあいます』
イラク戦争が始まる数日前から、僕は曲を作り始めました。ただ反戦の声を上げるのではなくミュージシャンとして出来ることは、感じ思うことを音楽で表現することだと思ったからです。
10日ほどスタジオにこもって6曲ベーシックトラックを作り、それからFree Electroのメンバーを呼んでオーバーダビングをはじめました。8月6日広島原爆の日に、自主制作で発表・発売したいと思っています。
Free ElectroはIMAバンド以来、10年振りに日本人のメンバーで作ったバンドです。テクノロジーと人間の力をミックスした、21世紀型の新しいバンドだと思います。Free Electroで"Over The Rainbomb"をひっさげて全国各地でライブをやろうと燃えています。どうか宜しく!
■ 近藤等則さんのCDジャケットの、アートディレクションをしていた。
「近藤等則 Spiritual Nature 第一弾 - Over the Rainbomb -」
国内販売は、ビクターミュージカルトレーディング。
ジャケットの題字は黒田征太郎さんである。
http://kitazawa-office.com/SPN/spn01.html
若い読者には説明が必要かもしれない。
近藤さんは、Jazzトランペッター・プロデューサーとして世界的に有名な方である。とりわけ、アメリカ・ヨーロッパでの評価が極めて高い。
近年は、2000年「Mt. Fuji Aid 2000」、2001年「ダライ・ラマ14世提唱 世界聖なる音楽祭・広島2001」をプロデュース。
NHKの「地球を吹く」シリーズでは、ネゲブ砂漠、アンデス山脈などの大自然と対峙して入魂の演奏を行なってきていた。映画、CMなどへの出演も多い。
最近では、ビクターエンターテイメントからの「THE 吉原」が好評。
栄芝師匠×近藤等則のコンビは、秋から冬にむけて各地を廻る。
■ ここでマウスをクリック。ブラウザを立ち上げて欲しい。
「青い瓶の話」のために、近藤さんが書いてくれたテキストはこれである。
http://kitazawa-office.com/SPN/spn05.html
■ 近藤さんとお会いしたのは、松岡正剛さん主催のパーティである。
私はかつて「編集学校」の三期・不良のセンセだったもので、珍しく定価で買ったブーツなどを履いて会場の隅にいた。
近藤さんは栄芝師匠、鈴木清順監督などと並び、壇上で挨拶をされていた。
大混雑の一次会が終り、二次会で酒が入る。二言三言、近藤さんと話をして、「THE 吉原」のサンプル版をいただいた。
夏のはじめ。
空気がくぐもって湿る夜、私は信濃町で行なわれた会合を終え、一人で青山墓地界隈を歩いていた。普段は車で移動するのが常だが、酔うと歩く。
いつのまにか六本木ヒルズの手前につく。
手前に隠れたラブホテルがあり、その価格などを眺め、坂道を昇ると窓が開かれたBarがあった。カウンターに見覚えのある顔が並んでいる。
私は一度通り過ぎ、それから引き返してBarの中に入った。
定番のウィスキをストレートで貰い、飲み干して会計を済ます。
帰り際、見知った顔に声をかける。いつぞやのサンプル版のお礼である。
そこからは、こっちきて飲めの世界であり、いつの間にかJazz談議に華が咲くことになった。
「サッチモが死んでJazzの太陽が落ちた。マイルスが死んで、Jazzの月も隠れてしまった」オレは朝日の取材にそう答えたんだ。それから、電話口で暫く泣いていたよ。涙がとまらねえんだ。
近藤さんはそんなことを言う。78年にNYに渡った時に、マイルスに呼ばれたことがあるという。でも、オレはいかなかった。いったらオレはトランペッターじゃなくなるじゃないか。
前後の脈絡と詳しい事情は聞いたが忘れた。確かそんな話をした覚えがある。
ブルーノートの何番台。そのジャケットの話。
私はジンのストレートを二杯三杯。いつの間にか腕まくりをしている。
なんだかよくわからないが、旨い酒だったとおもう。
不良の大先輩とともに酒を飲む。
男として、これがどういうことかはわかるだろう。
■ 八月の終わり、事務所の壊れかけたソファで漠然としていると電話が鳴る。
墓地はいりませんか、というものかと思って出ると「近藤等則です」と名乗った。実はね、と話はここからである。
数日後、送られてきた音のデモ版を聴く。
部屋で聴き、仕事場で聴き、それから車の中で聴いた。音の厚味というものがもしあるのだとして、それから終焉に向かう苛立ちと不安があるとして、この音楽は日本という枠組みを超えている。その速度、広がり。
逆説的に言えば、だからこそ「THE 吉原」のような音を見つけ、構築することができるのだろう。
お世辞ではなく、ビッグ・アーティストの音だと私は思った。
それから他の仕事を一切止め、数日の徹夜を含むデザイン・ワークスと、関係各位・各社への調整作業が始まったのである。
2003_09_29 北澤 浩一